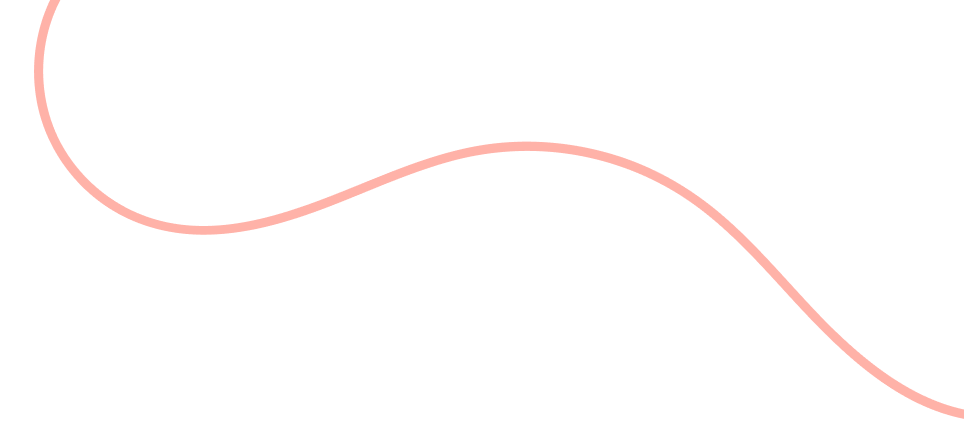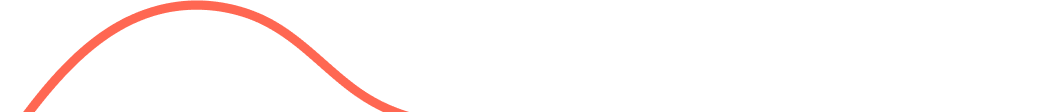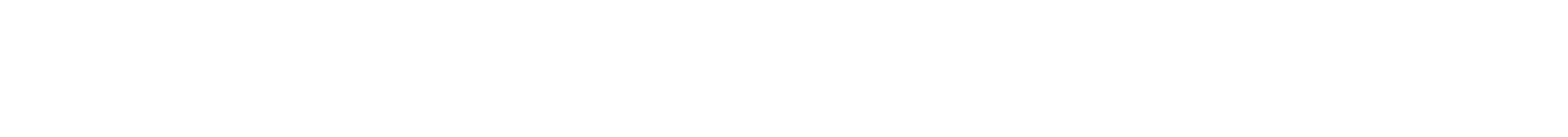マルコポーロの東方見聞録に登場したジパング
13世紀のヨーロッパでは、日本の存在はほとんど知られていませんでした。そんな中、イタリアの商人マルコポーロが著した旅行記によって、日本は「黄金の国ジパング」として世界に紹介されます。
この記述は、当時のヨーロッパ人に強烈な印象を与えました。遠い東方の海に浮かぶ島が、宮殿も民家も黄金でできているという話は、まるで夢物語のように響いたのでしょうか。では、マルコポーロはなぜこのような記述を残したのでしょうか。
イタリア商人マルコポーロが記した旅行記
マルコポーロは1254年頃、イタリアのヴェネツィア共和国で生まれました。商人の家系に生まれた彼は、1271年に父と叔父に同行し、アジアへの長い旅に出かけます。
パミール高原やゴビ砂漠を越えて元の都に到着したマルコポーロは、フビライ・ハン(元の皇帝)に仕えました。約24年間にわたる旅の中で、彼は元の各地に使節として派遣され、アジアの情報を収集していきます。
1295年にヴェネツィアに帰還した後、ジェノヴァとの戦争で捕虜となったマルコポーロは、獄中で同房の物語作家ルスティケロ・ダ・ピサに旅の体験を口述しました。これが『東方見聞録』として記録され、後世に伝えられることになります。
原題は『世界の記述』といい、4冊の本から構成されています。日本については3冊目に記述されており、ヨーロッパで初めて日本の存在を伝える貴重な記録となりました。
ジパングという名前の由来と語源
「ジパング」という呼称は、中国語の「日本国」の発音に由来しています。当時の中国南部方言では「ジッポングォ」と発音されており、これがヨーロッパ風に変化して「Cipangu(チパング)」や「Zipangu(ジパング)」となりました。
マルコポーロが元に仕えていた13世紀後半は、ちょうど日本が元寇を受けた時期と重なります。1274年と1281年の2度にわたる元の日本侵攻は失敗に終わりましたが、この出来事により中国では日本への関心が高まっていました。
マルコポーロは実際に日本を訪れたことはなく、中国滞在中に聞いた情報をもとに記述を行いました。特に泉州などの港町で活動していたイスラム商人から情報を得ていた可能性が高いとされています。
この「ジパング」という呼称は後に変化し、英語の「Japan(ジャパン)」の語源となりました。現代でも使われる日本の英語名は、マルコポーロの記述に端を発しているのです。
東方見聞録に書かれた日本の姿
東方見聞録によると、ジパングは「カタイ(中国北部)の東の海上1500マイルに浮かぶ独立した島国」と記述されています。この地理的な位置関係は、実際の日本の位置とある程度一致していました。
マルコポーロが記した有名な記述は、宮殿に関するものです。「王の宮殿は純金で覆われており、私たちが教会の屋根を鉛で覆うように、宮殿の屋根はすべて純金で覆われている」という一節は、ヨーロッパ人の想像力をかき立てました。
さらに「宮殿の床には、厚さ2指分の金の板が敷き詰められており、窓も金でできている」「莫大な金を産出し、財宝に溢れている」といった記述が続きます。こうした描写から、ジパングは黄金と宝石に満ちた理想郷として描かれました。
人々の風習についても詳しく記されています。「ジパングの人々は外見が良く、礼儀正しい」「偶像を崇拝する者(仏教徒)がいる」「葬儀は火葬か土葬であり、火葬の際には死者の口の中に真珠を置いて弔う習慣がある」といった記述は、当時の日本の特徴をある程度正確に伝えています。
日本が黄金の国と呼ばれた理由
マルコポーロが記した「黄金の国」という表現は、決して根拠のない誇張ではありませんでした。実際、当時の日本では豊富な金が産出され、特に東北地方は東アジア有数の産金地として知られていたのです。
なぜ日本は黄金の国と呼ばれるようになったのでしょうか。その背景には、平泉を中心とした奥州藤原氏の繁栄と、中国との交易で使われた大量の砂金がありました。この黄金伝説は、やがて遠くヨーロッパにまで伝わることになります。
平泉を拠点とした奥州藤原氏の財力
奥州藤原氏は11世紀末から12世紀にかけて、現在の東北地方一帯を支配した豪族です。初代清衡から4代約100年にわたって繁栄を極め、平泉は平安京に次ぐ日本第二の都市となりました。
清衡は前九年の役、後三年の役という戦乱を経て、1094年頃に平泉に館を移しました。戦乱で多くの肉親を失った清衡が望んだのは、平和な世の中をつくることです。そのため、敵味方を含めた全ての人々の霊を慰め、弔うために中尊寺の建立を始めました。
平泉の繁栄を支えたのは、東北地方で豊富に産出された砂金でした。奥州藤原氏は玉山金山をはじめとする金鉱山を一括管理し、この膨大な産金と南北交易による利益によって、京都をしのぐほどの文化都市を築き上げたのです。
清衡は京都から優れた技術者を呼び寄せ、中尊寺をはじめとする数多くの堂塔や庭園を造営しました。その財力は、当時の日本において群を抜いたものだったといえるでしょう。
中国との交易で流通した大量の砂金
日本が「黄金の国」として中国で知られるようになった背景には、遣隋使以降の外交使節が滞在費用として砂金を持参したことがあります。日本の使節が大量の砂金で支払いを行う姿は、中国人に強い印象を与えました。
奥州藤原氏の時代には、北方との交易も活発に行われました。初代清衡は白河の関から津軽半島の外が浜まで、一町ごとに笠卒塔婆を立て、金色の阿弥陀像を描かせたと伝えられています。藤原氏は津軽地方を含む北奥にも強い支配力を及ぼしていました。
南方との交易では、海路も頻繁に利用されました。中尊寺の仏像制作を依頼する際、二代基衡は支度料を運ぶために海船を使用し、大量の練絹を送ったことが『吾妻鏡』に記されています。
こうした交易活動によって、日本の金は東アジアの経済圏に広く流通しました。特に元の時代には、モンゴル帝国の広大な交易ネットワークを通じて、日本の金の評判がユーラシア大陸全体に広まったと考えられます。
ヨーロッパ人の憧れを集めた黄金伝説
東方見聞録が書かれた当時のヨーロッパは、ルネサンスの開花期に相当します。自由と解放を求める時代の気運の中で、「黄金の国ジパング」は東方の海に浮かぶ理想郷として渇望されました。
当時のヨーロッパでは金も香辛料も極めて貴重な物資でした。東方見聞録の記述は、多くの言語に翻訳され、手写本として広まっていきます。マルコポーロの言っていた内容は当初は信じ難いものでしたが、次第にヨーロッパの人々の心をとらえていきました。
この黄金伝説は、単なる富への憧れだけでなく、未知の世界への探求心を刺激しました。ジパングという名は、15世紀から16世紀にかけての大航海時代において、探検家たちを駆り立てる原動力となります。
1525年に出版された地図には「Zipangri」と大きく記載され、1570年のオルテリウスの地図帳にも「ヴェネツィアのマルコポーロはこの島をジパングリと呼ぶ」という説明書きがありました。ジパング伝説は、こうして世界の地図に刻まれていったのです。
中尊寺金色堂が象徴する平安時代の黄金文化
東方見聞録に記された「宮殿や民家は黄金でできている」という記述は、中尊寺金色堂の様子が誇張されて中国に伝わったものではないかという説があります。実際、金色堂は平泉文化の黄金時代を今に伝える象徴的な建造物です。
奥州藤原氏初代清衡によって1124年に建立された金色堂は、極楽浄土の世界を具現化しようとした当時の人々の願いが込められています。では、なぜこれほどまでに黄金を使った建造物が造られたのでしょうか。
純金で装飾された極楽浄土の再現
金色堂は、内外に金箔が押された「皆金色」と称される建造物です。堂内の内陣部分には、はるか南洋の海からシルクロードを渡ってもたらされた夜光貝を用いた螺鈿細工、そして象牙や宝石によって飾られています。
建立された当時は、仏法が衰退する「末法思想」が信じられていました。極楽浄土の姿をできるだけ具現化しようとした藤原清衡の切実な願いが、この豪華絢爛な装飾に表れています。金色の輝きは、苦しみのない理想の世界を象徴していたのです。
中央の須弥壇には阿弥陀如来が安置され、両脇に観音勢至菩薩、六体の地蔵菩薩、持国天、増長天を従えています。須弥壇を囲む「巻柱」は蒔絵、螺鈿、金で豪華に飾られており、極楽浄土に住むという半人半鳥の迦陵頻伽を描いた「金銅華鬘」は柔らかい金色の輝きを放っています。
金色堂の内部には3つの須弥壇があり、それぞれの内部に置かれた棺には、初代清衡、二代基衡、三代秀衡の遺体と四代泰衡の首級が今も納められています。遺体を安置する墓所を兼ねる阿弥陀堂というのは、他に類を見ない特徴です。
東北地方で産出された豊富な金資源
平泉の金文化を支えたのは、東北地方の豊富な金資源でした。日本で初めて金が産出されたのは奈良時代の陸奥国です。現在の岩手県や宮城県を含むこの地には、約4億5千万年前から1億年前につくられた金鉱脈が眠る特異な地質が広がっています。
玉山金山は岩手県陸前高田市に位置し、膨大な量の金と良質な水晶を産出しました。この金山で採れた金は、奈良時代に建立された東大寺大仏像に使われたことでも知られています。気仙地方には玉山金山の他にも、鹿折金山、大谷金山などの金鉱山がありました。
砂金採りは地域に浸透し、北上山地や沿岸部の産金地は奥州藤原氏にとって重要な財源となりました。宮城県気仙沼市と南三陸町にまたがる霊峰田束山には、奥州藤原氏ゆかりの寺院跡や経塚群が残り、産金地と平泉との深いつながりを伝えています。
戦国時代になると、鉱石から金を取り出す技術が確立され、伊達政宗が金山奉行を置いて直接開発を進めました。こうして東北地方は、1250余年に及ぶ日本の産金史が紡がれた稀有な場所となったのです。
国宝第1号に指定された歴史的価値
中尊寺金色堂は、明治時代以降、国庫の補助により数度にわたる本格的な修理が行われてきました。第二次世界大戦後に文化財保護法が制定されると、金色堂は1951年に国宝建造物第1号に指定されます。
1962年には解体大修理が行われ、建立当初の輝きを取り戻しました。江戸時代の俳人松尾芭蕉も金色堂を訪れ、「五月雨の降り残してや光堂」という有名な句を詠んでいます。この句は、戦乱で多くのものが失われたが金色堂だけは奇跡的に残ったという意味が込められています。
2011年には「平泉-仏国土を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群-」として世界文化遺産に登録されました。これにより、金色堂は日本だけでなく、世界的にも認められた文化遺産となったのです。
現在、金色堂は900年前に建立された当時の姿のまま残った唯一の建造物です。平泉に花開いた素晴らしい文化の光として、今も多くの人々を魅了し続けています。平和を願って造られた極楽浄土の象徴は、時代を超えて私たちに大切なメッセージを伝えているのです。
東方見聞録の記述と実際の日本の違い
東方見聞録に記されたジパングの描写は、実際の日本と一致する部分もあれば、大きく異なる部分もあります。マルコポーロは日本を訪れたことがなかったため、記述には伝聞と事実が混在していました。
当時のヨーロッパの人々にとって、極東の島国は完全に未知の存在でした。では、東方見聞録のどの部分が事実で、どの部分が誤解だったのでしょうか。黄金の国ジパングの実像と虚像を見ていきましょう。
マルコポーロは日本に来ていなかった
マルコポーロが実際に日本を訪れていなかったことは、現在では確実視されています。彼が元に仕えていた時期は1275年から1292年頃とされ、ちょうど元寇(1274年、1281年)の時期と重なっています。
東方見聞録には、フビライが日本征服のため軍を送ったが暴風で船団が壊滅したという記述があります。しかし、その年代を1239年としているなど、明らかな誤りがあります。実際の元寇は1274年と1281年に行われました。
また、「生き残った兵士たちが日本の都を占領し、7ヶ月間支配した」という記述もありますが、これも史実と異なります。こうした誤りは、マルコポーロが中国で聞いた話をそのまま記録したことを示しています。
マルコポーロが使っていた泉州という港町の名称は、イスラム商人の間で主に使われていた呼称でした。このことから、彼は日本についての情報をイスラム商人から得ていた可能性が高いと考えられています。実際に見たことのない土地について、伝聞をもとに記述したのです。
伝聞と事実が混在する記述内容
東方見聞録の記述を詳しく検証すると、正確な情報と誤った情報が混在していることがわかります。「ジパングは大陸から1500マイル(約2400キロ)離れた東の海に浮かぶ島国」という記述は、実際の距離とは大きく異なります。
実際の日本と大陸の距離は、対馬から朝鮮半島までが約50キロメートル、福岡市からでも約250キロメートルです。1500マイルという数字は、明らかに誇張されたものでした。これは、中国からさらに遠く離れた神秘的な国というイメージを強調するためだったのかもしれません。
一方で、日本人の特徴については比較的正確な記述もあります。「外見が良く、礼儀正しく穏やかである」「偶像を崇拝する者(仏教徒)がいる」「火葬の習慣がある」といった記述は、当時の日本の文化をある程度正しく伝えています。
「宮殿や民家は黄金でできている」という記述は誇張ですが、中尊寺金色堂のような豪華な建造物の情報が伝わり、それが膨らんだものと考えられます。部分的な事実が、伝聞を通じて拡大解釈されていったのです。
食人文化や香辛料に関する誤解
東方見聞録には、明らかに事実と異なる記述も含まれています。最も問題となったのは、食人文化についての記述です。「捕虜を捕らえた場合、もし身代金を支払えなければ、彼らは捕虜を殺して料理して食べる」という内容が記されています。
この記述によれば、「人肉が他の肉よりも優れており、非常に美味であると考えている」とまで書かれていました。しかし、日本の歴史において、このような食人文化が広く行われていた証拠はありません。これは、東南アジアの他の島々の話が混同された可能性があります。
香辛料に関する記述も誤りでした。東方見聞録では、ジパングを含む東南アジア全体が黒胡椒や白胡椒などの香辛料が豊富であると記されています。しかし、実際には日本は香辛料を豊富に収穫できる国ではありません。
当時のヨーロッパでは香辛料も金と同様に貴重品でした。こうした誤った情報も、ジパングを「豊かな資源を持つ理想郷」として描く一因となりました。マルコポーロは東南アジアの複数の地域の情報を、ジパングの記述に混入させてしまったのです。
世界史に影響を与えたジパング伝説
東方見聞録に描かれた「黄金の国ジパング」は、単なる地理的情報を超えて、その後の世界史に計り知れない影響を与えました。この幻想的なイメージが、ヨーロッパの探検家たちの冒険心を大いに刺激したのです。
15世紀から始まった大航海時代において、ジパング伝説は探検家たちを未知の海へと駆り立てる原動力となります。その結果、人類史上最も重要な発見の一つにつながることになりました。
コロンブスの新大陸発見につながった航海
クリストファー・コロンブスは、東方見聞録の熱心な愛読者でした。彼が所持していた東方見聞録の写本には、計366箇所にも及ぶ書き込みがあり、特に黄金の国ジパングの記述部分には多くのメモが残されていました。
コロンブスは地球球体説に基づき、西回りでアジアに到達できると考えました。彼の目標は、東方見聞録に描かれたジパングや中国、インドといった富める東方の国々に到達することだったのです。特にジパングの発見は、航海の重要な目的の一つでした。
1492年8月3日、コロンブスはスペインのパロス港から3隻の船で出航しました。10月12日、バハマ諸島のサン・サルバドル島に到達した彼は、この地をインドの東側だと信じ込み、現地の人々を「インディオ」と呼びました。
コロンブスは死ぬまで、自分がジパングの近くまで到達したと考えていたといわれています。実際には彼はアメリカ大陸に到達していたのですが、その事実には気づきませんでした。彼が大航海で見つけたエスパニョーラ島(ハイチ島)をジパングと断定したのも、黄金の飾りを身につけた島民の話を誤解したためでした。
大航海時代を促した黄金への憧れ
大航海時代の探検家たちを駆り立てたのは、黄金への欲望でした。コロンブスがスペイン国王に宛てた1503年の報告書には、「金はもっとも価値あるものであり、金こそ宝です。これを持っている者は、この世で欲することは何でもでき、天国へ魂を送り込むことができる地位にさえ達しうるのです」と記されています。
当時のヨーロッパでは、権力の基盤となる官僚制度や常備軍を維持するために、莫大な財源が必要でした。スペインやポルトガルの王室が探検家たちを支援したのは、新たな富の獲得が国家の繁栄に直結していたからです。
東方見聞録は後の大航海時代に大きな影響を与え、アジアに関する貴重な資料として重宝されました。コロンブスだけでなく、マゼラン、バスコ・ダ・ガマなど、多くの探検家がアジアを目指しました。ジパング伝説は、こうした探検家たちの原動力となったのです。
15世紀から17世紀にかけて、ポルトガルとスペインが切り開いた航路を、オランダやイギリスが続きました。バルトロメウ・ディアスの喜望峰回航、ヴァスコ・ダ・ガマのインド航路開拓、マゼランの世界周航など、歴史に残る偉業が次々と成し遂げられていきます。
現代に受け継がれる日本のイメージ
ジパング伝説は、現代にも影響を与え続けています。英語で日本を意味する「Japan(ジャパン)」という言葉は、「ジパング」が変化したものです。この呼称は、マルコポーロの記述を通じて世界中に広まりました。
実際、16世紀になると日本の金はさらに重要な役割を果たします。戦国時代から江戸時代にかけて、金は国内経済の基盤となり、また国際貿易でも重要な輸出品となりました。特に16世紀後半から17世紀前半にかけては、日本は世界有数の金・銀の産出国として、国際経済に大きな影響を与えたのです。
「黄金の国ジパング」というイメージは、日本が豊かで独自の文化を持つ国という認識を世界に広める役割を果たしました。マルコポーロの記述には誇張や誤解も含まれていましたが、日本が金の産出国であることは事実でした。
現在でも、日本は技術力や経済力で世界をリードする国として知られています。「黄金の国」という表現こそ使われなくなりましたが、豊かで魅力的な国という日本のイメージは、ある意味でジパング伝説の延長線上にあるともいえるでしょう。東方見聞録が伝えた日本の姿は、700年以上を経た今も、形を変えて世界の人々の心に残り続けているのです。